このコンテストは受付を終了しました

大賞
きみのゆくえに愛を手を
『ブラザーズ・ブラジャー』と改題し、加筆・修正、続編の書き下ろしを加えたものが、河出書房新社さんから刊行されました。
佐原ひかり
青春 完結
1時間16分 (45,522文字)
準大賞
あるはげた日に
キヨミは直径1.5センチの秘密を隠し通そうと決意した
坂水
青春 完結
56分 (33,331文字)
特別賞
これカノン
主人公が何歳かは、読み手によって変わります。
鯨井一
青春 完結
42分 (25,093文字)

最終候補作品
おやじドロップキック
私のために 夫と息子が戦うなんて 最高じゃない?
真江島 志絽
ヒューマンドラマ 完結
1時間0分 (35,945文字)
開花の忘れもの
幕末から明治へ変わる激動の時代を生き抜いた柔術家の娘の物語です。
Maro(お休み中)
歴史・時代 完結
59分 (34,882文字)
あるはげた日に
キヨミは直径1.5センチの秘密を隠し通そうと決意した
坂水
青春 完結
56分 (33,331文字)
これカノン
主人公が何歳かは、読み手によって変わります。
鯨井一
青春 完結
42分 (25,093文字)
きみのゆくえに愛を手を
『ブラザーズ・ブラジャー』と改題し、加筆・修正、続編の書き下ろしを加えたものが、河出書房新社さんから刊行されました。
佐原ひかり
青春 完結
1時間16分 (45,522文字)



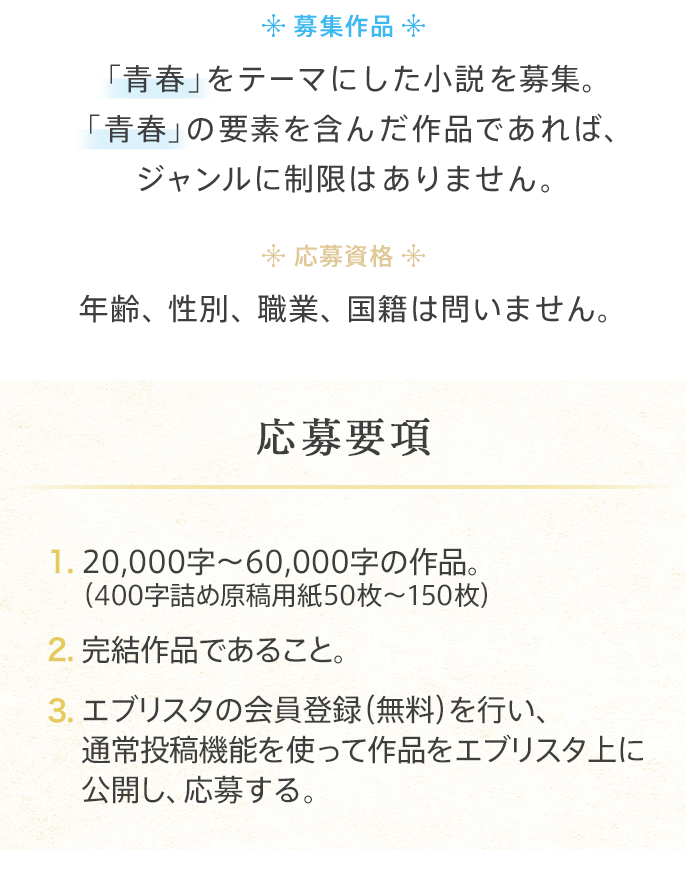


コンテストの注意事項(必読)




